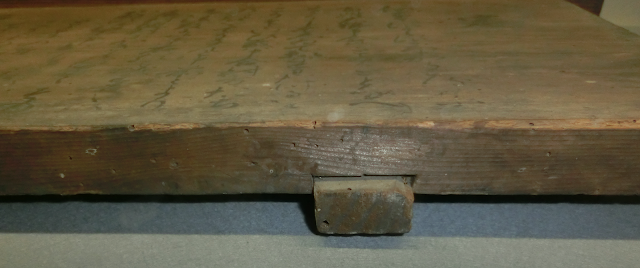普段の生活ではそれ以前の古典力学、ニュートン力学で事足りる。
無学なジジイは恥じ入る。
「GPS衛星の時計と地表にある時計では時間の進み方が違う」のだそうだ。
どのくらいの誤差が生じるかと言うと、
1日でGPS衛星は、0.0000286sec 時間の進みが遅くなる。
こんなのわずかどころか無視しても大丈夫じゃん、ではないのだ。
光速は30万km毎秒だから、
300000km/sec ✕ 0.0000286sec/day = 8.58km/day
一日あたり約9kmも誤差が出てしまうことになる。
GPSでこんなに誤差が出てしまったら使い物にならない。
理屈はこんなところだ。
a)特殊相対性理論では、光速に近づくと時間の進みが遅くなる。
b)一般相対性理論では、強い重力場の時間の進みは、弱いそれよりも遅い。
またGPSは高度20200kmを約3.9km/secの速度で周回軌道をとんでいます。
なので、
高度20200kmよりb)の理由で、GPSの時計の進み方はは地上に比べて早くなる。
約3.9km/secの速度よりa)の理由で、遅くなる。
この2つの誤差は相殺されずに、結果として
「1日でGPS衛星は、0.0000286sec 時間の進みが遅くなる」となります。
この例の他にも、相対性理論が日常の生活に応用されている事柄にはどんなことがあるのでしょうか。
興味がわきます。
パッとおもいつくのは、月に行って戻ってきたり、ハヤブサなどの小惑星観測のときにも
当たり前のように使われているのだろうということは想像できるな。